勉強が得意なだけでなく、ITやスポーツ、アートなどの多様な「強み」を持つ人材が求められる昨今。将来に向けて子どもの「強み」を伸ばしたいけれど、「我が子の強みって何だろう?」という保護者も多いはず。そこで注目したいのが、【やる気スイッチグループ】の習い事。我が家の息子の強みも見つかった、その体験を詳しくレポートします!
今回参加したイベント『AKASAKAあそび!学び!フェスタ』とは?
『AKASAKAあそび!学び!フェスタ』は、TBSテレビが主催する参加費無料の親子向けイベント。

子どもたちにワクワクする「あそび」を通じて「学ぶ」楽しさを伝えることを目的としていて、幼児から小学生を対象に、さまざまな企業と連携した多彩なコンテンツが展開されます。
2024年の初開催に引き続き、2回目の開催となった今回は2025年4月4日(金)からの3日間、東京都港区の赤坂サカス広場およびTBS赤坂BLITZスタジオ周辺にて開催。今年も大盛況のうちに幕を閉じました。
PR
ゲーム感覚で楽しすぎ! 息子も夢中になった「プログラミング教育 HALLO」の体験
最初に我が家が向かったのは、【やる気スイッチグループ】と日本を代表するAI開発企業・プリファードネットワークスから誕生した「プログラミング教育 HALLO」の体験が用意されたブースエリア。

幼稚園の年長から中学生を対象としていて、タイピングやプログラミングの基礎から実践スキルまで学べるカリキュラムが特徴です。
実は偶然にも、春休みに別の塾のプログラミング教室を数回体験したばかりの息子。どんな腕前を見せてくれるのでしょうか……⁉
さっそく体験開始! タブレットに表示された3Dキャラクターから、好きなほうを選んでタッチします。

すると、画面上に可愛らしいロボットが出現‼

このロボットを移動させて「星」を取るプログラミングに挑戦するんですって。
プログラミングというと、真っ黒な画面にたくさんのコードが書かれているところを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、ご安心ください! プログラミング教育 HALLOでは、コードを書く代わりに、視覚的に分かりやすいカラフルなアイコンやブロックで表現された「ビジュアルプログラミング言語」からスタート。

指示の書かれたブロックを指で動かすなどの直観的な操作でプログラムを作成できるため、低年齢の子どもでも学びやすいのが魅力なんです。
説明が終わると、コーチといっしょにプログラミングに挑戦。

ロボットをどう動かせば星が取れるかを考えながら、サクサクとブロックをつなぎあわせてプログラミングを作成する息子。おぉー、春休みの経験が生きているようですね。
再生ボタンを押すと、息子の思惑どおりにロボットがマスを進んで星をゲット。

見事ステージクリアとなりました。わぁー、今どきのプログラミングって、ゲーム感覚で身につけられるんですねー。 楽しすぎるーーー‼
ステージが進むごとに、ただマスを進めるだけでなく、ロボットを回転させるなどプログラミングの難易度は徐々に上がっていくのですが、自力でクリアしようと頑張る息子。

試行錯誤を繰り返す中で、うまくいったときの達成感は大きいよう。「ほらできたよ!」という息子のドヤ顔が印象的でした。これなら遊んでいる感覚で、いつの間にかプログラミングが身につきそう!
実用的なコーディングまで身につけることができる教材「Playgram™(プレイグラム)」には、自由にモノをつくって3D空間をデザインできるステージもあるのだとか。

「こんなのつくってみたい!」が、子どもたちのやる気の源となりそうですよね。
今回の体験で息子がプログラミングを得意げに楽しむ様子を見て、「これって息子の強みなのかも。だとしたら伸ばしてあげたい!」と思った筆者。

しかも2025年度の大学共通テストから、プログラミングを含む「情報I」が必須科目となっていて、プログラミングが将来の進学や就職に役立つスキルであることは間違いなさそう。ますます息子に習わせてみたいと思いました。
あまりにも意外! 科学の力で子どもの運動能力を育てる「忍者ナイン」
続いて息子が参加したのは、オープンスペースで開催された「やる気スイッチON!忍者クイズで運動の豆知識を学ぼう!」。

【やる気スイッチグループ】が展開するスポーツ教室「忍者ナイン」によって用意された体験プログラムです。
「できれば運動ができる子に育ってほしい」とくに男の子の親ならそう願う方は多いはず。筆者も密かにそう思っていたので、「忍者ナイン」はとっても気になっていた習い事のひとつでした。
そのネーミングからして、てっきり忍者修行のような内容で身体能力を磨くのだとばかり思いこんでいたのですが、実はまったく違っていました!

サッカー、野球、バスケ、テニス、陸上競技……あらゆるスポーツには、種目に合わせた体の動かし方があります。その根幹にある9つの基本動作を、スポーツバイオメカニクスの研究成果を基に考案されたプログラムで習得する幼児・小学生向けスポーツ教室が「忍者ナイン」。将来どんなスポーツをする場合にも役立つ、いわば運動動作の礎が身につくんだとか。頼もしいですよね!
今回用意されていたのは、運動がうまくなるためのコツが問題となったクイズ。
最初のお題は「ジャンプ」。高くジャンプするコツは、次の2つのうちどちらでしょう?というものでした。
1:腕を大きく後ろに振って跳ぶ

2:腕を高く上げてから跳ぶ

「えー、どっちだろう?」と戸惑いの表情を見せた息子でしたが、実際に2つともチャレンジしてみて違いを感じ取ったよう。見事「1」の正解を選ぶことができました。
ジャンプするときはつい「足」にばかり目が行きがちですが、スポーツバイオメカニクスの視点で分析すると、実は「腕」の動きも重要。腕を大きく後ろに振って飛ぶと、振り子のような反動が生まれ、高く跳ぶことができるんですって。
次のお題は「走る」。速く走るためのコツは、2つのうちどちらが正しいかを選びます。数年前に近くの公園で参加したかけっこ教室で確か教わった気がするのですが、そのコツはもはや忘却の彼方です。
1:前に出した脚と同じ腕を出す

2:前に出した脚と反対側の腕を出す

実際に1と2のそれぞれのポーズで構え、一歩を踏み出すところまでチャレンジして考えます。「えーと、どっちだったっけなー?」と迷っている様子の息子でしたが、勘や感覚を頼りに正解の「2」を選ぶことができました。
こちらもジャンプのときと同様に、腕の「反動」を使うのが重要なポイント。だから踏み出す足と逆の腕を引くんですね。理由までしっかり理解できたら、もう忘れなさそうです(笑)。
難問だったお題が「組む」。踏ん張って立つコツは、どちらが正しいでしょう?というものでした。
1:つま先を閉じて立つ

2:つま先を開いて立つ

うーん、これは悩みますよね。踏ん張って立つというと、なんとなくつま先を開いているイメージがあるような……。あれこれ悩んだ結果、息子も筆者も「2」の開いて立つをチョイス。ところが正解は「1」の閉じて立つでした。ざ、残念!
力強く踏ん張るときのカギは、足の親指の付け根にあるプクッと膨れた部分「母指球(ぼしきゅう)」にあるのだそう。ここでしっかり地面を押すようにすると、重心が安定し、力強く踏ん張れるんですって。説明を聞いたあとに、実際にやってみると確かに力強く踏ん張れました!
そのほか「投げる」「打つ」「取る」「蹴る」の計7つのお題に挑戦しました。なんとなく正解が分かるものが多かったですが、その一方で「なぜそうなのか?」と聞かれると答えに詰まるものばかり。忍者ナインでは、それらを全部学んで身につけられるんだからすごいですよね。
ちなみに忍者ナインでは、動作分析シミュレーションシステムを用いて、子どもたちの今の運動能力を「見える化」。さまざまなプロスポーツ選手の分析結果データと照らし合わせ、どんな競技に向いているかを診断してくれるんです。

こうした科学的な診断結果をもとに子どもの隠れた才能を見つけて、一人ひとりに合った指導で伸ばしてくれるんですって。素敵すぎますねー!
子どもに運動系の習い事をさせたいけれど、何が向いているか分からないという方も多いはず。まずは忍者ナインを始めてみるのもおすすめです。
まとめ
今回の体験で気づいたことは、子どもの隠れた「強み」を見つけることの重要性。子どもの「強み」を見つけて今から伸ばしてあげれば、将来の選択肢を大きく広げてあげられますよね。我が家は、息子の強みの一つがプログラミングだと分かり、ぜひ伸ばしていきたいと考えています。

我が子には特別な才能はないかも……というあなた。子どもの強みを見つける方法の一つとして、「プログラミング教育 HALLO」や「忍者ナイン」などの新たな習い事に挑戦してみるのはいかが。どちらも無料体験レッスンを実施中です(一部、無料で実施していない教室もあり)。気になる方は、ぜひ最寄りの教室に問い合わせてみてください。
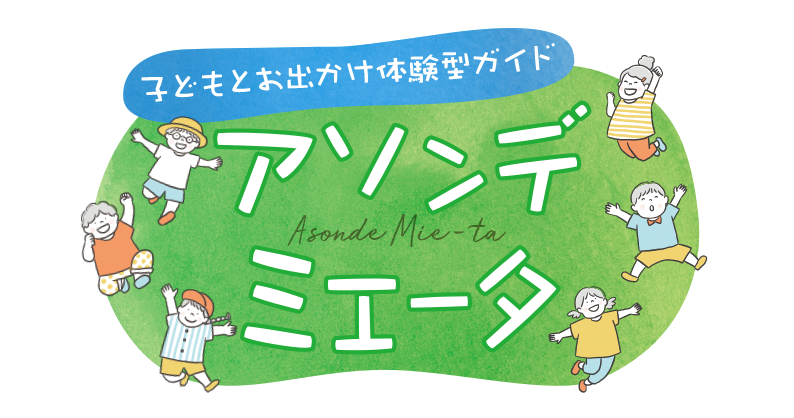








コメント